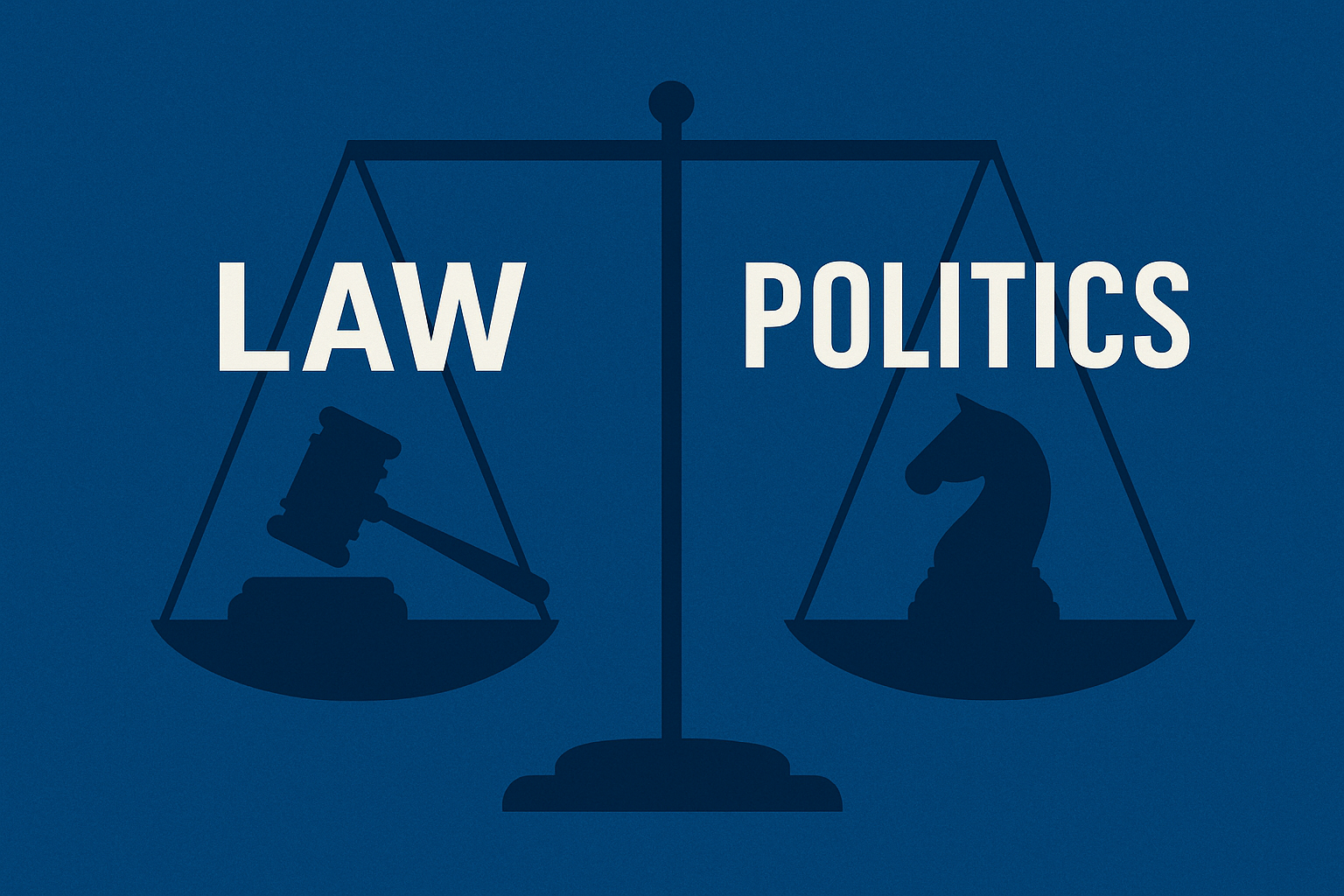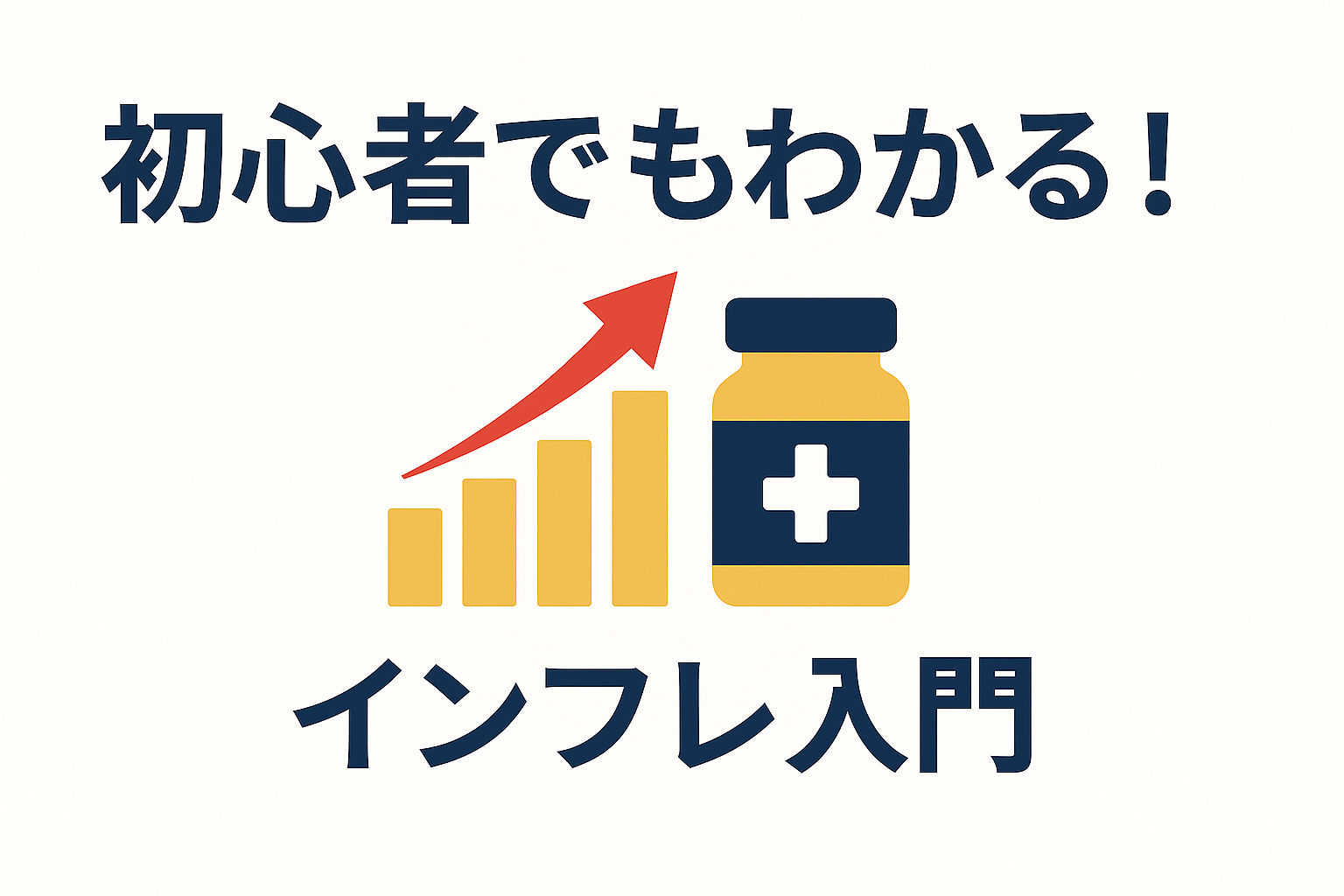──“疑わしきは罰せず”を無視する政治劇
最終更新日:2025年8月29日
8/29更新分は、文末に記載がございます
※追加内容:時系列の確認・ファクトチェック(事実確認)・リークされたタイミング・政権の動き・クック理事の動き
■ はじめに
世界の視線がジャクソンホールに集まるさなか、FRB理事リサ・クック氏に「住宅ローン二重申請」疑惑が浮上し、政権サイドからは早々に「辞任せよ」の圧力が掛かりました。
しかし、法治国家の基本である「疑わしきは罰せず」はどこへ行ったのか。
そして…これは個人のスキャンダルではなく、FRB独立性を揺さぶる政治劇なのかもしれない。
と、ふかちん&GP君はキナ臭さを感じました。
■ 何が起きているのか(疑惑と政治的圧力)
報道ベースで整理すると、論点はこうです。
クック理事が住宅ローン申請で「主たる住居」を二重に記載した疑いがある――という“未立証の疑惑”が浮上しました。これは、米国司法省(DOJ/Department of Justice)に同内容の「告発文」が届いたという所から発したニュースになります。
ただし、告発文というよりも「〇〇さんと△△さんは不倫をしています!」という昼メロに出てきそうなドラマの小道具の「怪文書」っぽく、真偽の程は判りません(そもそも、発信元は?)
それに対し、トランプ政権側からは、なぜか「直ちに辞任を」というメッセージが飛んだ訳です。
一方のクック氏は「いじめには屈しない」「辞めない」と明言し、圧力に抗う姿勢を示しました。
ここで重要なのは、正式な立件や確たる証拠が現時点では公に確認されていないという点です。
にもかかわらず政治が先行し、世論を動員して辞任へ追い込もうとする構図が生まれています。
■ 法治国家の原則 vs 政治のショートカット
近代法治国家の根幹にあるのは「疑わしきは罰せず(In dubio pro reo)」
これは大前提です。確たる証拠を集め、裁判を行い、裁判官が判決を下す。
そして、大切なのは「三審制」大審院で確定するまで、裁判で争う事が出来ます。
又、司法ー立法ー行政は、三権分立の基本に則り、越権する事は出来ません。
では、今回の件を振り返ってみましょう。
本来の筋は、①適正手続(調査)→②事実認定→③責任の有無と処分、となるのが最低限の筋でしょう。ところが今は「疑惑(未立証)→辞任要求」というあまりにも短絡的な手続のショートカットが起きているのです。
これ、裏がありそうでしょ?私たちもそう思いました。
そして、さらに見逃せないのはタイミングなんです。
世界の市場がジャクソンホールに神経を尖らせ、視線が集まる週に、こうした“別の火種”を投じるのは、注目の主軸をずらし、相手の正統性を削ぐ典型手法でもあります。
悪い言い方をすると、「北の方の大国が、国際イベント(主に冬季五輪)開催の裏で争いごとを仕掛ける」ような、政治的演出と情報戦の重ね技に近いやり方です。
結論を急ぐのではなく、手続への忠実さが不可欠――ここを外せば、法が政治に従属する危うい前例だけが残ります。
■ 「本当にやるか?」という合理性の壁
では、リサ・クック氏は、本当に二重請求をやったのだろうか?
という疑問ですね。
直感的にも、FRB理事=金融の頂点に立つ人物が、リスクリターンの合わない“小さな不正”をわざわざやるのか?という疑問がつきまといました。
- 得るものは小さい:住宅ローンの条件で得られるベネフィットは、理事職と信用を失うリスクに比べて微々たるもの。
- 失うものは巨大:職、名誉、研究者としてのキャリア、制度全体の信頼。割に合わないことは明白だ。
- むしろ“ハメられる”側:FRBの理事という地位は常に“うまみ、利権を狙う魑魅魍魎の標的”であると言えます。何とかお知り合いになり、何としてもうまみを吸いたい。
又、あの人を蹴落とせば”私があの地位になれるかも”と、よこしまな考えを持つものも少なからずいる訳です。
すると、偽造書類・誇張リーク・政治目的のスケープゴート化…仕掛ける側がコストを小さく、リターンが大きく得られる構図のほうが現実的。
もちろん、事実関係は最終的に手続で確かめるべきですが、合理性の観点から見れば「二重申請のような“小技”を理事自らやる必然性は薄い」というのが第一印象だと思いませんか?
■ 過去の前例:理事の“有罪”は見当たらず
歴史的に見ても、FRB理事(Board of Governorsのメンバー)が不正で有罪判決を受けた公的記録は見当たりません。
問題が摘発された事例は理事ではなく、顧問や職員に関するものが中心。
たとえば、元上級顧問の機密持ち出しでの起訴や、職員による規程違反――いずれも理事本人の刑事有罪とは別次元の話である。
だからこそ今回のケースは、「制度の象徴」を狙った政治的揺さぶりという読みが自然に強まるのです。
重要なのは、“前例なき強度の政治圧力”を、立証前の疑惑に乗せているという点
■ クック理事のプロフィールと象徴性
では、今回トランプ大統領にロックオンされた、クック理事のプロフィールを見ていきましょう。
リサ・D・クック氏は、FRB史上初のアフリカ系アメリカ人女性理事として2022年に就任、翌年再任され、任期は2038年までと長期にわたり米金融政策の中枢を担う存在。
学歴は、Spelman Collegeで物理学と哲学を修め、オックスフォード大学でPPE(哲学・政治・経済学)を学び、カリフォルニア大学バークレー校で経済学博士号(PhD)を取得という、まさにエリート中のエリートです。
職歴も、ミシガン州立大学教授として経済史やイノベーション研究に従事し、オバマ政権では国家経済会議(CEA)上級エコノミストとして政策立案にも関与した実績を持つ人物。
ウォール街の実務家というより、制度設計と学術研究で勝負してきた人物。
だからこそ、「住宅ローンの二重申請」という“小さな不正”をわざわざリスクを冒してまでやる合理性は極めて薄い。むしろ、象徴的な立場だからこそ狙われやすいと見る方が現実的ではないでしょうか。
■ 何を仕掛けられているか(パウエルからクックへ)
私たちは前稿で「パウエル爺、最後の意地」を扱った。そこでの焦点は、政治の“深い利下げ圧力”にFRBがどう耐えるかでした。
今回のクック疑惑は、その延長線上にあると推測できないでしょうか。
すなわち、
- 人事を通じて政策を変える(気に入らない理事は辞めさせ、同調的な理事に差し替える)
- しかも立証前の疑惑をテコに、世論で包囲して辞任へ追い込む
仮に誤りだったとしても、トランプ流の政治では「ごめん」で幕引きにしながら、結果(相手の弱体化・差し替え)は既成事実化する可能性があるのです。
これは法の支配と制度の独立に対する、静かだが深刻な挑戦だといえます。
追記(2025年8月26日)
パウエル議長は最長でも来年2月で任期が終了します。
で、今回クック理事が退任したとしましょう。で、トランプ派の理事が入ったとします。
そうすると… 実は、トランプ派が過半数を上回るんですね。
何か… 怪しい、香ばしいカホリがしてきませんか?
■ 今後の分岐点(チェックリスト)
- 手続の動き:正式な調査の開始有無、証拠の開示、第三者的検証。
- FRB・議会の反応:独立性を明確に支える声明や行動が出るか。
- 人事の兆候:辞任圧力に呼応する形で“差し替え”の布石が打たれるか。
- 市場の受け止め:金融政策の予想(利下げ・利上げ)に、人事ショーがどう織り込まれていくか。
ポイントは、「立証前に結論を出さない」こと。事実ならば相応の責任を問うべきだし、事実でないなら法治と独立性を守るため、むしろ圧力の側にコストを支払わせるべきだと思います。
結論
この件は、クック個人の好き嫌いでも、単なるスキャンダルの優劣でもない。問われているのは、法治の筋を通すか/政治の号令で飛ばすか、そしてFRBが独立性を保てるかなのです。
「疑わしきは罰せず」――その当たり前の原則を、私たちはもう一度思い出す必要があるでしょう。ジャクソンホールの陰で起きているのは、制度の信頼をめぐる戦いでもあるのです。
追記(2025年8月26日)
トランプ大統領はSNS上で「クック理事を即時解任する」と発表しました。しかし、法的根拠は曖昧であり、FRB理事を「for cause(正当な理由)」で解任できるかについては明確な前例が存在しません。専門家の多くは「政治的パフォーマンスに過ぎず、法的効力は極めて限定的」と指摘しています。
一方、クック理事本人は「大統領にその権限はない」として辞任を否定。米国司法省(DOJ/Department of Justice)がパウエル議長に宛てたとされる解任要請書簡についても、議長には解任権限がなく、実際の効力は不透明です。
つまり現時点では、「解任宣言」と「辞任拒否」がぶつかり合い、制度的には膠着状態にあります。市場やメディアにとっては派手なニュースであっても、制度面から見れば“怪文書政治劇”の色彩が強いといえるでしょう。
今後の展開予測と対応
- 公式調査や司法手続きへの進展が確認されれば、個別スキャンダルから制度問題へと昇華し、体系的な議論が可能になる。
- 進展がなければ、「just us(身内の都合)」ではなく「just me(俺ひとり)」に近い独断政治として、制度の独立性を脅かす前例になりかねない。
今のトランプ大統領に『justice(正義)』はあるの?
米国司法省(DOJ・Department of Justice)は存在するが、そこに宿っているのがjustice(法の正義)なのか、それとも“just us/just me”なのか──。この問いが、今回のクック理事疑惑の核心に浮かび上がってきています。
現在、ファクトチェック(事実確認)が出来ておりません。全て「うわさレベル」でニュースサイトも右往左往している状況です。
公式には何も出ていません。つまり、全て「怪文書」レベルの話だという事です。
追記(2025年8月29日)
※時系列の確認・ファクトチェック(事実確認)・リークされたタイミング・政権の動き・クック理事
今回の怪文書報道について、時系列を追いかけて整理してみました。
ファクトとノイズが入り混じる中で、浮かび上がったのは──「公式にコメントを出したのはFRBだけ」「司法省もリークした?本人も沈黙」「現物は依然不明」……そして、クック理事が“幽霊のような事案”でキャリアを潰されかけている、という異様な構図でした。
1. 時系列の確認
- 8/21:ロイターが「米司法省のマーティン氏からパウエル宛にクック理事の不正を告発した書簡を渡す」と報道
- 他メディアが「ロイターによると」で追随した
- 米国司法省(DOJ)・リークしたとされる人物マーティン氏本人は完全に沈黙中(マーティン氏は非常にトランプに近い人物)
- クック理事側代理人である弁護士が「clerical error(事務的ミス)」の可能性を主張(不正ではなく過失の線を強調)
- FRBだけが「解任理由なし、司法判断待ち」と公式コメント
2. ファクトチェック(事実確認)
- 書簡の現物は未確認。もし本物なら、発生して10日以上経過しているはず(ジャクソンホール直前は、パウエル氏は会場入りしている。つまり最短でも前週=最低でも8月10日の週には見ているハズ)
- 当の米国司法省(DOJ)からの公式コメントは、一切なし → 情報源は極めて不透明。既に2週間経過…ここがハッキリすれば、かなりモヤが晴れるハズ
- FRBだけが「解任理由なし、司法判断待ち」と公式コメント→FRBは何もせずに公式にコメントは出さない。現状、何かあれば独立性を失うのはFRBだからだ。
必ず「ヒアリング」をしている。パウエル議長にもクック理事にもしていると思われる。
3. タイミングの不可解さ
- なぜジャクソンホール、パウエル氏の演説の真っ最中にリーク?
- 市場の注目をパウエル演説から逸らし、「政治ショー」にすり替える狙いか?
4. トランプ政権の動き
- SNSで「解任大統領令」を発表。
- ファクトが不確かでも、「解任した」という既成事実だけを先に打ち出してしまった。
5. クック理事の動き
独立性と法治国家の原則が試されている瞬間。「幽霊のような事案」でキャリアを潰されかけている。
トランプ大統領とは、法廷で決着するべく訴訟準備中
当ブログでは、引き続き本件の「真実」と「深読み」を続けます。
出典
- Reuters(2025年8月25日・26日・29日)
- Bloomberg, WSJ, Financial Times 各紙報道(2025年8月25日・26日)
関連記事
・”トランプという現象”を中立に読み解く
・次期FRB議長は誰だ!【候補者一覧】
・スティーブン・ミラン氏暫定FRB理事候補に指名
・初心者でもわかる!連邦準備理事会/米国中央銀行(FRB)入門