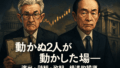カテゴリ:FRB議長候補シリーズ|プロフィール|最終更新日 2025年9月6日(JST)
■ フルネーム・生年月日
本名:Kevin Allen “Kev” Hassett
生年月日:1962年3月20日(現在 63歳)
■ ポジション早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金融スタンス | ややタカ派(成長優先だがインフレには警戒) |
| トランプとの関係性 | 極めて近い(政権内の中核ブレーン) |
| 特記事項 | 元CEA委員長/「忠臣型」経済理論家/再登用の可能性が高い |
■ 略歴と注目ポイント
- 学歴と研究基盤
ハセット氏はボストン・カレッジで経済学士号を取得後、ペンシルベニア大学で博士号を取得。博士論文は「財政政策と景気循環」に関するもので、政策立案の現場に応用できる実証分析を中心に構成されました。
学生時代から「理論を政策へ」と意識しており、その姿勢は生涯一貫しています。 - FRBスタッフ時代(1980年代後半)
FRBの経済スタッフとしてマクロ予測モデルの開発を担当。議事録作成の裏方として金融政策決定に必要なデータを提供し、金融市場の変動を定量的に分析する立場を経験。
この時代に培った「数字で語る姿勢」が、のちのCEA委員長としての強みとなりました。 - CBO(米議会予算局)での実績(1990年代)
経済予測部門の上級エコノミストとして、均衡予算法の分析や社会保障改革案の経済効果を試算。
赤字削減や歳出抑制を巡る議会の攻防を目の当たりにし、「経済理論を現実政治に落とし込む」力を磨きました。 - AEI研究員として(2000〜2017年)
アメリカン・エンタープライズ研究所(AEI)で20年以上にわたり政策研究に従事。特に法人税制の改革と年金制度に関する研究は著名で、議会証言や主要メディアへの寄稿も多数。共和党系のシンクタンクに所属したことで、保守派経済政策の理論的支柱としての地位を確立しました。 - CEA委員長(2017〜2020年)
トランプ政権発足直後にCEA委員長に指名され、2017年の大型減税法案「Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)」の成立を理論面から支えました。
議会証言では「法人減税が企業投資を促し、労働者の所得を底上げする」と繰り返し主張。政権の看板政策を学問的に裏付ける存在となりました。 - パンデミック期の復帰(2020年)
- 経済危機の只中でホワイトハウスに呼び戻され、「経済を閉じれば失業率は20%に達する」と発言。
迅速な財政出動を強く提言し、数千億ドル規模の景気対策の一部形成に影響を与えました。
この“非常時のブレーン”としての役割は、2025年の再登用論議につながっています。
■ 政策スタンス
- 成長志向のタカ派
基本的には経済成長を優先するが、インフレを軽視しない姿勢から「成長志向のタカ派」と呼ばれています。緩和一辺倒ではなく、ドルの信認維持を重要視しています。 - 法人減税の旗振り役(2017年)
議会公聴会では「税率引き下げは投資と雇用を同時に刺激する」と証言。
企業投資が増えれば生産性向上と賃金上昇につながるという理論を展開し、共和党の政治的説得材料として活用されました。 - 規制緩和の一貫性
AEI時代から一貫して「規制は成長のブレーキになる」と指摘。特に金融規制の簡素化を主張し、市場の効率性と競争を優先する立場をとっています。 - パンデミック期の強い警鐘
2020年春、「経済活動を全面停止すれば、失業率は戦後最悪の水準に達する」と発言。段階的な経済再開の必要性を訴え、その後の対策法案に影響を与えました。
▷ 減税と賃金(公聴会・講演での発言要旨)
- 「法人税率の引下げは、設備投資を誘発し、生産性の改善を通じて賃金へ波及する」
- 「投資が強い時期ほど労働需要は底堅く、低賃金層の雇用が回復しやすい」
- 「減税の便益は“株主だけ”ではない。賃金・雇用・価格の複数経路で家計に届く」
▷ インフレと金融政策(記者会見・寄稿の要旨)
ハセット氏はインフレについて「成長を損なわない範囲での安定」を最重視してます。
- 「利下げは手段にすぎず、インフレ期待を安定させることが目的」
- 「インフレ抑制と成長促進はトレードオフではなく、両立可能」
特に2020年のパンデミック時には「過度な緩和はドルの信認を損ねる」と警告しつつ、必要な局面では迅速な財政出動を推奨しました。この「タカ派とハト派の間を行き来する柔軟さ」が、彼の最大の特徴です。
- 「インフレ期待を安定させることは成長政策の前提条件」
- 「緩和は必要だが、過剰にするとドル信認を毀損する。成長と物価の均衡が最重要」
- 「利下げは“目的”ではなく“手段”。成長エンジンを止めない範囲で運営するべき」
▷ パンデミック期の失業見通し(インタビュー要旨)
- 「経済活動が長期停止すれば失業率は短期間で二桁台後半〜二〇%に達し得る」
- 「景気の底割れを防ぐには“迅速な財政出動+段階的再開”の両輪が必要」
- 「景気対策は一気呵成、出口はデータ次第で慎重に」
※上記はハセット氏の過去の証言・発言の趣旨を整理したものです(逐語ではありません)。逐語引用を入れる場合は該当資料の引用範囲をご確認ください。
法人減税の理論的根拠と波及効果
ハセット氏が最も強調してきたのは「法人税率引き下げが経済全体にプラスの波及をもたらす」という理論です。
特に、2017年のトランプ政権下で成立した大型減税法(TCJA)の際、彼は議会公聴会やメディア出演で次のようなロジックを展開しました。
- 設備投資の増加
→ 減税で企業のキャッシュフローが改善 → 設備投資拡大。 - 生産性の向上
→ 投資による機械更新・デジタル化・自動化で労働生産性が上昇。 - 賃金の押し上げ
→ 生産性上昇の果実が従業員に分配され、賃金増加に繋がる。
この「トリクルダウン型」理論は、共和党の説得材料として大いに利用されました。一方で、民主党からは「企業の自社株買いに流れ、賃金まで波及していない」と批判され、後に統計を巡る論争を生みました。
国際協調と通商政策への影響
ハセット氏は、国内政策の理論家でありながら、国際舞台にも言及してきました。
- 日本に対しては「円安ドル高の是正」を求めた発言歴があり、為替政策への関心も強い。
- 中国に対しては「為替操作国」認定に理論的根拠を与え、対中強硬姿勢を学術的に補強しました。
つまり、FRB議長に就任すれば、純粋な金融政策だけでなく、国際通商・為替の論点を絡めて発言する議長像が想定されます。
■ 政治との関係性
- 政権の「通訳」
- トランプ大統領の直感的で政治的なメッセージを、経済理論へと翻訳し、議会や市場に伝える存在。「政権の意図を数字で補強する忠臣型」として評価された。
- 再登用の現実味
- 2025年夏、トランプ大統領は「ハセットは最有力候補の一人」と明言。政権への忠誠心と即応力から、再登用の可能性が極めて高いと見られる。
- 議会での評価の分裂
- 共和党からは「学問と実務を両立する数少ない存在」として支持。一方、民主党からは「政権寄りすぎてFRB独立性に懸念」と批判される。上院承認では独立性が最大の焦点となる。
- 他候補との比較
- ウォーラー氏(理論派タカ派)、ボウマン氏(現場型の豪傑)、ベッセント氏(財務長官。債権の神様であり実務家)
この中でハセットは「忠臣型の調整役」として政権に安心感を与えています。
■ 影響分析
日本への影響(事例ベース)
- 為替市場:利下げに慎重であれば、日米金利差は拡大し、円安基調が続く可能性が高い。自動車・半導体といった輸出産業には恩恵。
- 輸入コスト増:一方でエネルギーや食料の輸入価格上昇に直結。特に中小企業や家計に影響が及ぶ可能性。
- 日本国債市場:米金利が高止まりすれば、日本の長期金利も上昇圧力にさらされ、日銀の金融政策に柔軟性を欠かせる状況に。
日本(業種別の想定インパクト)
- 自動車:ドル高・円安が収益を押し上げやすい。対米需要が底堅ければ北米販売の利益率改善。一方で米国の税制優遇・規制緩和が国内投資を米国へ振り向ける誘因に。
- 半導体:データセンター投資やAI需要拡大が続く前提なら製造装置・材料に追い風。ただし米国の対中規制強化の度合いによってサプライチェーン再編コストが発生。
- 食品輸入:ドル高は輸入価格の上振れを通じて小売価格・外食コストに波及。特に畜産飼料・油脂・小麦系で家計負担増の公算。
- 電力料金:原料のLNG・石炭がドル建てで上がりやすく、電力原価→規制料金への転嫁圧力。エネルギー多消費産業のコスト高に留意。
- 金融:日米金利差が広がる局面では円キャリーが再燃しやすい。為替ヘッジコストの上昇は機関投資家の外債運用に影響。
新興国への影響(シナリオ分析)
- ドル建て債務リスク:トルコ、アルゼンチン、エジプトなど外貨債務の多い国は、ドル高による返済負担増に直面。
- 資本流出圧力:利回りを求めた資金が米国に還流するため、新興国市場からの資金流出が加速する可能性。
- 一部の恩恵:米国経済が拡大すれば、輸出依存度の高いアジア諸国(ベトナム、インドネシアなど)には追い風。
- 「ドルショック」懸念:政策次第では急激なドル高が起き、新興国通貨危機の火種となり得る。
新興国への影響(国別シナリオ)
- トルコ/アルゼンチン:慢性的なインフレとドル建て債務が多く、ドル高→返済負担増→通貨下落の悪循環に陥りやすい。短期資本流出に注意。
- エジプト/パキスタン:外貨流動性の薄さから、IMF支援と緊縮の同時進行が必要になり、成長と物価のトレードオフが強い。
- インド:内需が厚く相対的に耐性は高いが、外資流入の変動と原油高が重なると経常収支の悪化に注意。
- インドネシア/ベトナム(東南アジア):米国成長の恩恵で輸出需要は底堅い一方、通貨安・輸入インフレの圧力。政策金利の先回り的な引締めで通貨を防衛するシナリオ。
- メキシコ:地政学的にニアショアリング追い風。ただし米金利高止まり時は比ペソ同様に通貨ボラティリティが高まりやすい。
- ブラジル:コモディティ価格の動向次第では輸出収益の下支えも、金融条件タイト化で国内信用の伸び鈍化に注意。
補足:共通の波及経路
- 米成長>利下げ慎重 → 2) 金利差・ドル高 → 3) 輸入インフレ/外貨債務負担増 → 4) 家計・企業コスト上昇 → 5) 政策対応(補助金・利上げ・為替介入)。
国・業種ごとの差は「外貨負債の多寡」「一次産品の輸出入構造」「政策余地」で決まりやすい。
リスク・批判と反論
批判① 「Yesマン化で独立性を失う」
- 懸念点:ハセット氏はトランプ大統領と極めて近い人物であり、「政権の意向を優先するのでは」との不安が常につきまとう。
- 反論:ただし、彼自身は「インフレ期待を壊す政策は許さない」と繰り返し述べており、必要な場面では政権に異を唱える可能性も残しています。
批判② 「理論先行で現実を見誤る」
- 懸念点:法人減税による賃金上昇は十分に実現していないと指摘され、「机上の空論」と批判する声もある。
- 反論:しかし、彼は「短期の結果ではなく、5年・10年のスパンで見れば成果が出る」と主張。中長期の投資行動を見据えた分析を重視しています。
批判③ 「市場ボラティリティを高める危険」
- 懸念点:タカ派寄りの金融政策を志向する場面では、利上げや高金利長期化で市場が動揺する可能性。
- 反論:他方で、ハセット氏は「前もって十分な説明を行い、市場との対話を重視する」と強調。透明性を高めることでショックを和らげられるとの信念があります。
批判④ 「民主党の強い抵抗」
- 懸念点:議会承認過程で民主党から「政権寄りすぎ」「FRB独立性を損なう」との批判が必至。
- 反論:一方で共和党内での信頼は厚く、また経済学者としての知的蓄積とメディア発信力を評価する声も多い。承認戦を突破できるかは、上院の議席配分にかかります。
■ GP君の一言
「“困ったときのハセット”は政権にとって安心のカード。
でも、市場からは“独立性を欠いたFRB議長”と疑われるジレンマに直面するだろうね。」
出典先
- FRB公式経歴資料
- CEA公式記録(2017〜2020年)
- American Enterprise Institute(AEI)研究論文・寄稿
- The Wall Street Journal(2025年7月報道):「ハセット氏が再登用の有力候補」
- Reuters(2025年6月25日):「トランプ氏が“3〜4人の中にハセット氏”と明言」
- Kiplinger(2025年7月):「FRB議長後任候補分析レポート」
- Bloomberg, Financial Times(2020〜2025報道):「ハセット氏の政策スタンスと議会での評価」
関連記事リンク
👉 他の FRB議長候補のプロフィールもぜひチェック