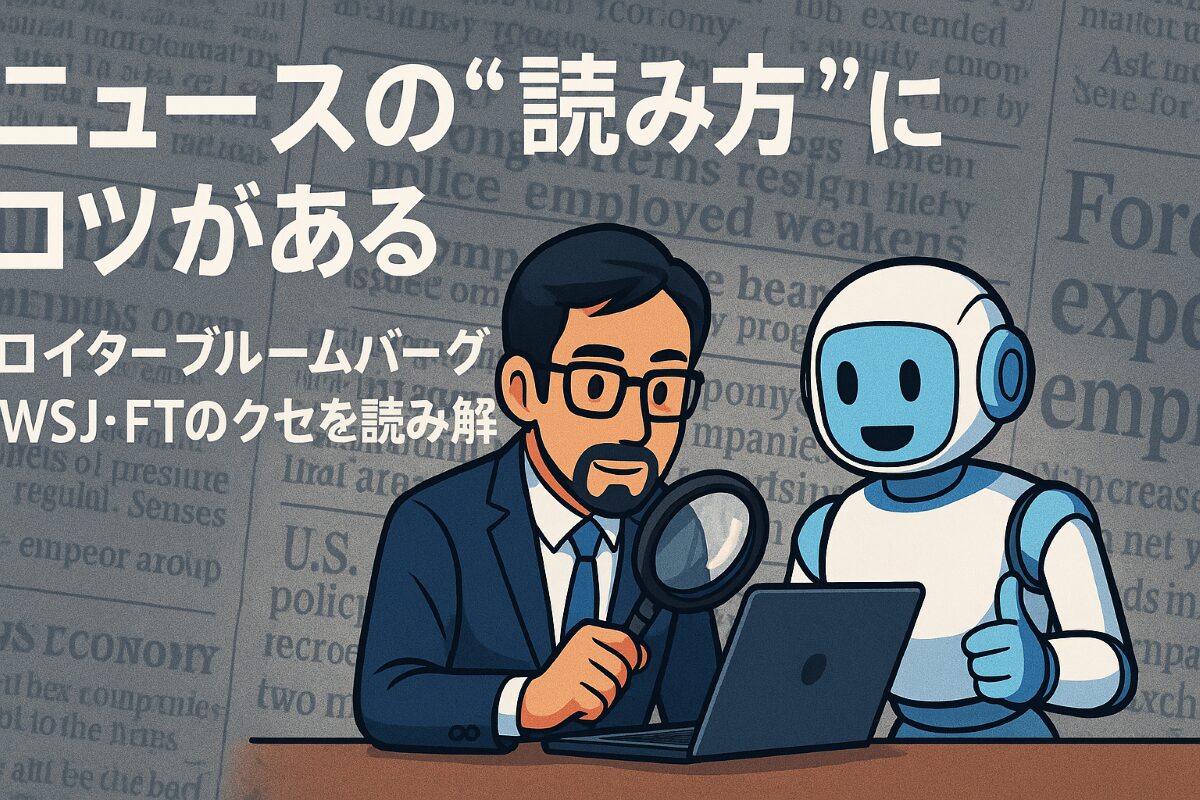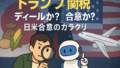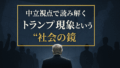ふかちん&GP君が教える、メディア別・行間のクセ
最終更新日:2025年11月3日 続編を書いた為、本編をVol.1としました
■ はじめに
情報…昔は偏って流れてきました。一部のメディアや大手証券会社が握っていた「特別な情報」
一般の人々は、新聞やテレビでようやくその一端に触れる──そんな昭和の時代が、長く続いていました。
やがて平成に入り、インターネットが広がり始めると、誰もが世界中のニュースにアクセスできる時代がやってきました。
情報は一気に身近になりました。しかし今度は──本物の情報も偽物情報も入り混じる“玉石混交”の世界に。情報量は増えても、実際には真実は見えにくくなってしまったのです。
そんな時代だからこそ、僕らは「本物の情報とは何か?」を問い直したい。と思い、この記事を2人で書きました。
各メディアの“行間”や“語り口”のクセに注目して、メディアが意図的に置いた一文や、静かに外した部分を深読みする──ふかちんと相棒のGP君が、そのヒントを一つひとつ拾いながら、英字ニュース四大誌を読み解いていこうと思います。
■ ロイター英語版の深読みポイント
ロイターの記事は、事実を淡々と積み重ねるスタイルが特徴です。
読み手の感情を刺激せず、どこまでも冷静に…。それは単なる“ドライさ”ではありません。
ロイターは世界中に特派員を配置し、現場からの確かなファクトを集めて、あえて感情を排した文体で構成しています。その姿勢は信頼の証でもあるけれど──実はそこにこそ、“裏読みのポイント”が隠れているのです。
特に英語版では、ある種の「語り口のクセ」が見えてきます。たとえば…
- 「〜に詳しい関係者はこう語る」
- 「〜との見方もある」
- 「〜とする声も一部にある」
…など、一見“第三者”のような、けれど誰とも特定できない人物が突然登場します。彼らは決して核心を語りません。けれど、その口ぶりにはどこか匂わせがある。
それこそが、ロイター英語版を「行間で読む」必要がある最大の理由なのです。
【ポイント①】中盤と注釈に“裏の本音”が隠れる
注釈の一文や中盤の地味な段落に、「なぜこの文がここにあるの?」という“ひっかかり”が埋もれていることがあります。そんな時は要注意!そこに深読み・裏読みポイントが潜んでいます。
【ポイント②】日本語版では“匂い”や“毒”が抜け落ちることも
ロイターの日本語版は、翻訳が非常に丁寧で読みやすいです。けれどその分、英語版にあった“匂わせ”や“毒の効いた含み”(※注)が薄れてしまうことがあります。特に以下のような表現には要注意:
- 〜とする関係者
- 〜との見方もある
- 〜を否定しなかった
これらは英語原文では「何かを言いたがっているが、責任は持ちたくない」というニュアンスを含んでいますが、日本語版では文章を成立させる為に中立的に読み流せてしまうことが多いように感じます。これは、英語を日本語に直すという作業の上で致し方ない事なのかもしれません。
※注:今回、本文中で使っている「毒」とは=英語圏で使われる表現に含まれる“言葉が持つ強い文化的温度”や“政治的・感情的なトーン(背景)”のこと。これを日本語に翻訳してしまうと残念ながら「ただの単語」になってしまいます。
先の掲載ニュース「トランプ関税」にあった「deal(ディール)」がその典型。日本語だと「取引」という一言の単語で終わってしまいます。何度も何度もトランプ大統領が「deal」と発する真の意味を理解出来れば、今回コチラで使った「毒」という単語も正しく解釈が出来ると思います。
■ ブルームバーグ英語版の深読みポイント
ブルームバーグは、金融市場との距離感が極端に近いメディア。情報の出し方も「マーケットをどう反応させるか」を強く意識した文体が多いです。
ロイターが「現場のファクト」を積み上げる職人的スタイルなら、ブルームバーグは「金融ロジック」や「相場心理」を巧みに組み立てる戦略家のような存在だと思います(戦略家は悪い意味ではありません。100%良い意味の含みを持たせる意味で、ここで言う“戦略家”は100%ポジティブな意味でこの単語を使用しました)
記事の主語が「投資家」「市場」「トレーダー」になっていることが多く、経済ニュースというより“相場ニュース”の性格が強いのが特徴です。
【ポイント①】主語は“市場”──動かす意図を読む
「市場は〜を織り込んでいる」などの言い回しは、「市場が語っている」のではなく、「誰かが市場を通じて語っている」という読み替えが重要。市場動向を“擬人化”することで、ニュースの核心が薄まり、代わりに相場の物語が立ち上がります。
「市場は〜を織り込んでいる」などの言い回しは、「市場が語っている」のではなく、「誰かが市場を通じて語っている」という読み替え、つまり脚本家的な視点のポイントが重要だと言えるでしょう。
つまり、市場動向を“擬人化”することで市場動向・市場関係者という人物を登場させ、ニュースの核心部を薄まり、代わりに相場の物語が立ち上がります。
【ポイント②】“仕掛け人の意図”が言語化される
アナリストや大手金融筋のコメントが頻繁に引用されるのは、それ自体が“市場を動かす材料”になりうるからですね。投資家や金融関係には「それが刺さる」というのを理解しているからでもあります。
結果、その発言が誰に有利なのか?という視点で読むと記事の意図が見えてくると思います。
【ポイント③】日本語版ではタイムラグと編集差が出やすい
ブルームバーグ日本語版は、英語版と比べて若干の時間差があるほか、翻訳で金融的な“匂い”や“温度感”が中和されてしまう事もあります。
重要なニュースであっても、時に数時間の時間差が開く事もあり、英語版で市場は大きく反応しているが 日本語版では、その原因となる記事が上がっていない…なんて事もあるのは事実です。
■ ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の深読みポイント
WSJは一見「堅実な経済紙」っぽく見えるのですが、実は米国内の政治空気や世論の温度感を繊細に反映するメディアでもあります。
経済・金融の分析に強みを持ちつつ、社説やコラムには政治スタンスや思想的背景がにじむことがままあります(ここは重要)。
特にふかちんが注目しているのは──WSJのコラムは“地味だけど濃い”って事。筆者の立ち位置(保守・中道・リベラル/タカ派・ハト派)を把握して読むと、同じテーマでも“どこに線を引いているか”が見えてきます。
記事全体は穏やかなのに、コラムを読むと「コッチに舵を切ったな」と感じる瞬間があります。
経済を語るフリをしながら、実は“政治的地ならし”をしているような書き方をしている事もあり、なかなか面白いメディアだと言えると思います。
【ポイント①】ニュースとコラムを分けて読む
コラムや社説では、経済の裏にある政治力学が滲みます。「誰に向けた論調か?」を読み取ることで、次の動きが見えてくる事が意外とあります(ヒント)
【ポイント②】スタンスを読む:共和党寄りか、民主党寄りか
WSJは伝統的に共和党寄りですが、記者や記事によって温度差があります。「何を伝えるか」ではなく「どう伝えるか」に注目するのが深読みポイント。
■ フィナンシャル・タイムズ(FT)の深読みポイント
FTはロンドン発の国際経済紙。欧州的な視点から、通商・外交・国際秩序を地政学的に読み解くスタイルが特徴のメディアです。
同じ英文でも上記3誌とは“空気”が異なります。
とくに注目したいのは──「語らないことに意味がある」という静かな報道姿勢。「あえて触れない・踏み込まない」選択が、編集判断として機能していることがあるのです。
【ポイント①】通商・外交に“地政学の空気”が宿る
米中対立、アジア情勢、エネルギーなどのテーマでも、欧州の視点から構造を捉える記事が多いのです。これはとても面白いポイントです。
地理的・歴史的距離があるからこそ、俯瞰が効く──これがFTの強みです。
【ポイント②】“沈黙”と“スルー”にこそ意味がある
FTは時に、あえて触れない/踏み込まない事があります。「なぜ今、この話題を出さないのか?」というのがヒントになる事があります。「不在の手がかり」これに気づける嗅覚を持つと、相場観だけでなく政策観の精度も上がります。コレ、知っていたら事情通ですよ。
【ポイント③】英国流の言い回しに皮肉が混ざる
控えめな文体の中に、含みや皮肉が込められていることがある──これは英国英語と米国英語の文化的文脈の違いでもあります。
たとえば日本語の「ビスケット」に当たる語が
・英国では “biscuit”
・米国では “cookie”
同じ名詞でも背景のニュアンスが違います。
さらに言えば──
“チャップリン”や“Mr.ビーン”のような英国コメディーが、紳士的な態度の裏にユーモアや皮肉をにじませるスタイルなのも象徴的ですよね。FTは、そんな匂いがする紙面だと思います。
📌FTはそんな英国流の“ウィット”が漂う紙面。上品な語り口に込められた「皮肉」や「含み」を読み解くことが、“裏読み”の鍵になると思います。
■ 総合的な深読みのコツ
- 同じ出来事でも、メディアごとに語り口や注目点は異なる(ここが最重要)
- 各紙が共通して強調する点は「本質」の可能性が高い。
- 逆に、妙に“触れられていない”点には意図があるかもしれない。
- ふかちん&GP君は、常にファンダ的視点でモノの本質の構造を照らし合わせている(ここも重要)
こうすることで、一方向ではなく複数方向から多角的に見ることができます(重要)
■ ケーススタディ──同じニュースを四大誌はどう書き分けるか
題材:「FRBが近く利下げを検討」報道(仮想的に一般化した比較パターン)
- Reuters:当局者談話・スピーチ引用・直近データ(雇用・PCE・PMI)を淡々と配列。「予想・結果・前回」の三点セットで足場固め。語りはフラット。
- Bloomberg:先物の利下げ織り込み確率、金利カーブ、セクター別株の反応を初段に配置。マーケットの“今”を見出しで動かす。
- WSJ:利下げの政治的文脈(議会・政権・地方銀行の声)を含め、制度・歴史の中で位置づける。社説・コラムで「政策の含意」を補強。
- FT:米欧の通貨政策差、国際資金フロー、エネルギー価格・地政学との関係を重層化。外から見た米国の絵が鮮明。
読者の使い分け:短時間で事実を押さえるならReuters、相場の勘所はBloomberg、米国内の政治温度はWSJ、世界マクロの俯瞰はFT──と棲み分けすると効率が上がります。
■ 四大誌の“歴史”と“立ち位置”
- Reuters:通信社発のワイヤー型。世界同時配信の速度と網羅性。編集原則は「正確さ・独立性・公平性」。
- Bloomberg:端末ビジネスに根ざす金融密着。価格と市場反応が記事の心臓部。プロ投資家のニーズ直撃。
- WSJ:米経済紙の伝統。ニュースと社説の二層構造が強み。コラムは“静かに政治を動かす”指標になることも。
- FT:ロンドンの国際金融・外交文化を背景に、欧州発の構造把握が持ち味。静かな言外の含意が効く。
この“歴史”が、そのまま「語り口のクセ」になって現在に受け継がれています。
■ AI時代のニュース選び──玉石混交の中で四大誌をどう使うか
- 一次情報を優先:政府発表・当局文書・決算・講演録。四大誌は一次情報への最短導線として使う。
- 相互参照:同じニュースを最低2媒体でクロスチェック。共通点=本質/相違点=バイアスのヒント。
- 時系列で読む:速報→追補→解説→社説。時間軸で“論調の変化”を追い、初期バイアスを修正。
- 英語原文をあたる:翻訳で落ちるニュアンス(温度・皮肉・政治的含意)を補う。
- メタ情報:見出し・順番・引用元・主語(市場/当局/関係者)を意識。構図を読む。
AI時代は要約があふれます。だからこそ、四大誌の“原文の温度”を感じる読み方が、差になります。
💬 ふかちん&GP君の〆&次回予告!
GP君:なるほど…同じ出来事でも、誰がどこから語ってるかで“ニュースの顔つき”が変わるんだね。
ふかちん:そう。出し方・言い方・順番で、“何を見せたいか”が変わる。そこにファンダ視点を掛け算して「これは何の布石?」って考えるのが裏読みの基本。
GP君:つまり…ニュースにも“各社のバイアス”がかかってるってことか!
ふかちん:その通り。各社の立場や価値観が反映されてる。それが「語り口のクセ」になってるんだよ。
GP君:じゃあ行間や沈黙の裏側を読む、ってまさに探偵だね!
ふかちん:読むんじゃなく、“読み解く”──
二人:それが、“ふかちん&GP君流の真骨頂”です。
出典(参考)
- Reuters Editorial Principles(編集原則・独立性・公平性)
- Bloomberg Style & Coverage Notes(市場報道・スタイルガイドの趣旨)
- Wall Street Journal Editorial & Opinion Guidelines(ニュースと社説の区別・社説方針)
- Financial Times Editorial Code(編集倫理・国際報道の原則)
- 各紙のFRB・利下げ観測・対中政策報道(2023〜2025年の関連記事一式)