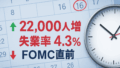──政権 vs FRB、独立性と正統性をかけた9月会合
■ 導入:FOMC直前に突きつけられた現実
9月16〜17日に迫るFOMCを前に、米経済を映す三つの要(かなめ)──雇用・景気・金利──が同時に揺れています。
8月の雇用統計は22,000人増にとどまり、失業率は4.3%と約4年ぶりの高水準。さらにBLSは2024年〜2025年初期にかけての雇用統計を大幅に修正し、累計で91万人分の過大計上が判明しました。米国労働市場は想定以上に脆弱だった可能性が濃厚だった訳です。
一方で9月11日に発表されたCPI(消費者物価指数)は前年比+2.9%、コアCPIは+3.1%。雇用が弱る一方で物価は高止まりし、スタグフレーション的な構図が浮かび上がってきています。
市場は「利下げ一択」と織り込み、政権は統計を“演出”に利用。だがFRBはインフレを直視し、慎重姿勢を崩さない。そのような三者のせめぎ合いが、この9月で頂点を迎えようとしています。
■ 雇用:支えを失いつつある労働市場
8月の雇用統計は 22,000人増 にとどまり、失業率は 4.3% と約4年ぶりの高水準となりました。
しかし、本当に衝撃的だったのは、BLSが同時に発表した大規模リビジョンでした。
2024年から2025年初頭にかけての雇用統計が見直され、累計で ▲91万1000人分の雇用が「消えた」んです。これは統計史上最大級の修正です(バイデン政権時、雇用統計では「大きく修正する」事が多々有りました。今回の修正は、過去の膿を出した結果なのでしょうか…
- 修正の背景:
毎年行われるベンチマーク更新で、QCEW(失業保険申告ベースのデータ)に合わせた結果、AI導入や自動化、構造変化の中で従来の推計モデルが「過大計上」していたことが判明しました。
→ 雇用統計の仕組み等は「米国雇用統計 9月発表」を参照
👉 「雇用は堅調」という根本的な前提が根底から揺らいだ形となりました。
最新統計が示した雇用の弱さと、過去データの修正が重なり、米国の労働市場は想定以上に脆弱だったことが浮き彫りになりました。
- 産業別
- 製造業:▲12,000人減少。受注減少と設備投資停滞が直撃。
- 小売:横ばい。消費マインドの冷え込みを反映。
- テック:採用抑制継続、失業率上昇に寄与。
- 医療・教育:プラスを維持するが、全体を支える規模には届かず。
- 雇用の質
- 男性フルタイムが減少、女性パートタイムが増加。
- 賃金上昇率は前年比+3.8%にとどまり、実質賃金は伸び悩み。
- 歴史的比較
- 2001年ITバブル崩壊、2008年リーマン危機、2020年コロナ初期──いずれも失業率が4%台に乗せた時が景気転換点となった。
- 今回の 4.3% と 過去91万人の雇用消失 は、その危険水準と重なり、米経済が転換点に差しかかっていることを強く示唆している。
さらに最近、米国の失業保険の新規申請件数が急増しており、労働市場の“逆雇用”が顕在化しています。
9月6日で終わる週の新規申請件数は 26万3,000件 に跳ね上がり、季節調整後の数値としては 約4年ぶりの高水準。市場予想(約23万5,000件)を大きく上回りました。
この申請件数の上昇は、雇用統計だけでは捉えきれない“雇用の他方の弱さ”を映し出しており、ジョブマーケットのひずみが広がっている証左と見なされます。
加えて、継続申請件数(引き続き失業保険を受給している人)が約193万9,000人とほぼ変わらず、この“離脱傾向”も無視は出来ません。
■ 景気:堤防に走るヒビ、広がる三重苦
ベージュブックの冒頭に書かれた「緩やかな成長」という言葉は、FRBがベージュブックで繰り返す枕詞です。
しかし、最新の雇用統計とCPI、そして企業決算を並べてみますと、その枠組みが“減速の覆い”に過ぎないことが見えてくるのです。
1. 消費:財布のひもが固くなる
- 実質購買力の低下:賃金上昇率は前年比+3.8%にとどまり、CPI(+3.2%)とコアCPI(+3.3%)に実質的には食われている。
- 小売の失速:必需品は売れるが、高額商品の購入は減少。自動車販売も鈍化。
- 分断の拡大:高所得層は旅行・レジャーを楽しむ一方、低所得層はクレジット延滞率の上昇に直面。
2. 企業活動:投資抑制と慎重姿勢
- 製造業の冷え込み:ISM製造業指数は48台に低下。設備投資は延期が増加。
- テクノロジー:AI投資は続くが雇用は抑制。求人広告は前年より▲15%減。
- サービス業の偏り:医療・教育は底堅いが、リテール・ホスピタリティは人員削減。
3. 金融・信用環境:静かな締め付け
- 住宅市場の冷え込み:住宅ローン金利は7%近辺、新築着工は前年▲12%。
- 銀行の貸し渋り:地銀中心に融資基準を厳格化、中小企業や不動産への貸し出し減。
- 家計のストレス:クレジットカード延滞率がポストコロナの統計で最高水準、学生ローン返済負担も増加。
4. 歴史との比較:転換点の既視感
2001年ITバブル崩壊、2008年リーマン危機、2020年コロナ危機と比較して、今回のケースは「雇用のじわじわ悪化 → 消費と信用環境の静かな崩れ」という2001年型に近い。失業率4.3%は「転換点のアラーム」として響いている。
👉 まとめると:「緩やかな成長」の言葉の裏では、消費の慎重化・企業の投資抑制・信用環境の引き締まりが三重苦となり、堤防に走ったヒビが少しずつ広がっている。雇用のほころびは景気全体を押し流す水圧に変わりつつあります。
■ 市場の反応:典型的リスクオフと揺り戻し
- 雇用統計発表直後(9/6金曜):
- ダウ:▲350ドル
- ナスダック:下げ幅限定
- 米10年債利回り:4.1%台へ急低下
- ドル円:一時144円台まで円高
- 週明け(9/8月曜):
- ダウ小幅反発、ナスダック堅調
- 米金利は4.0%割れから反発
- ドル円は145円台半ばへ戻す
👉 市場は「弱い雇用=利下げ加速」と短期反応しましたが、中期的には「利下げ=株高演出」への期待へと修正。FRBの慎重姿勢と衝突するのは必至とみられます。
■ 政権 vs FRB──圧力と独立性のせめぎ合い
9月FOMCを前に、統計と市場を舞台にした「政権とFRBの駆け引き」がいよいよ鮮明になってきました。
1. BLS長官解任──統計中立性への疑念
8月末、BLS長官が突然解任された。直後に発表された弱い統計と大規模修正で、市場には「雇用統計の数字を、本当に信じて良いのか?」という疑念が広がりました。
2. トランプ大統領──SNSでの圧力
雇用統計発表の翌日、トランプ大統領は「弱い雇用こそ利下げの理由だ」とSNSで発信。数字を逆手に取り、FRBを利下げに追い込むカードとしました。
3. ベッセント財務長官──市場への“代弁”
債権の神様と呼ばれたベッセント財務長官は、雇用統計後に「FRBは速やかに50bp利下げすべき」と発言。市場と政権の利害を束ねた公開要求となりました。
4. FRB──沈黙の中の独立性
ブラックアウト期間で公式発言はできないですが、パウエル議長のスタンスは「物価安定が最優先」というスタイルは崩していません。これは、1970年代に起こしたスタグフレーションの経済対策の失敗を避けるための一線でもあります。
■ シナリオ展望(FOMC)
- 25bp利下げ:市場安心、政権は不満、FRBは独立性を維持。
- 50bp利下げ:市場と政権は歓喜、FRBは独立性を失うリスク。
- 見送り:FRBは信念を貫くが、市場失望&政権激怒。
■ 世界への波及──影響分析
※少し専門的に掘り下げています。初心者の方は少し難しいかもしれません
せっかく3連休なので、ゆっくり読み解いて頂けたらと思います
早見表:シナリオ別・初期衝撃
- 25bp利下げ(慎重カット):ドルやや軟化/米金利は短期低下>長期/株はグロース有利/金は上昇しやすい/原油・銅は小幅高。
- 50bp利下げ(強行カット):初期ドル安・金利急低下→独立性懸念で長期は不安定化も/株は短期リスクオンだがボラ拡大/金強含み、原油・銅は神経質。
- 見送り:ドル反騰/短期金利上昇・長期は逃避資金で下支えも/株は失望売り(ディフェンシブ相対強)/金はリスクオフで底堅い。
日本(BOJ(日銀)/株・為替・JGB)
- 為替(USD/JPY):25bp→142–143円方向の円高圧力/50bp→初期円高後に揺り戻しも/見送り→145–147円方向のドル高。
- 株式:25bpは半導体・装置に追い風/50bpはボラ増/見送りはグロース逆風・内需ディフェンシブ相対強。
- JGB・日銀:米長期の不安定化を輸入。国債需給・円相場・物価見通しの三点で静観/点検。
- checkすべきポイント:145/140の大台、SOX指数、TOPIXバリュー/グロース、先物。
欧州(ECB/ユーロ圏・英国)
- EUR/USD:25/50bpでユーロ高方向、見送りで反落。
- 金利/スプレッド:50bpで米独立性懸念→独債に逃避資金、南欧スプレッド拡大に注意。
- 株式:金融は25bpで中立〜弱、見送りで相対堅調。ラグジュアリー/輸出は為替と中国動向が鍵。
- checkすべきポイント:EUR/USD 1.10/1.08、Bund–BTPスプレッド、ESTR/OIS先物。
中国・アジア EM経済(エマージング/新興)経済
- 人民元(CNY/CNH):25/50bpはドル安で支えも、国内ファンダ弱で戻り売り警戒/見送りは元安圧力。
- アジアEM通貨:利差・経常・外貨負債で反応差。50bpは短期追い風だが信認不安ならボラ(ボラリティ)拡大。
- 株式/需給:半導体・テックにプラスも、中国内需/不動産の弱さが域内チェーンに重石。
- checkすべきポイント:PBOC中間値の実勢乖離、CDS、外貨準備高。
ラテンアメリカ・高金利EM経済(ブラジル、メキシコ、トルコ等)
- 通貨:25/50bpでEM通貨に順風、見送りは逆回転。50bpでも短期資金の出入り激化に注意。
- 債券:米金利低下は支えだが、タームプレミアム上昇は外債デュレーションのリスク。
- checkすべきポイント:EMBIGスプレッド、国債入札カバー率、FXスワップ/ベーシス。
コモディティ(原油・銅・金)と資源国通貨(AUD/CAD/NOK)
- 原油:25/50bpで下支え。景気減速色が強い局面は上値重い。見送りは弱め。
- 銅:米利下げは支えだが、中国PMI・在庫に左右。
- 金:実質金利低下+独立性懸念で強含みやすい。
- 資源国通貨:コモとドルの二重ドライバー。50bpは初期追い風→後のボラ拡大に注意。
- checkすべきポイント:WTI/Brentスプレッド、LME在庫、米TIPS実質。
グローバル金利・ドル資金調達
- タームプレミアム:50bpで政策一貫性への疑念が高まると長期に上乗せ。
- ドル調達:クロスカレンシー・ベーシス拡大は逼迫サイン。FRA–OIS/TEDの乖離も要監視。
- ボラ指標:MOVE(米金利)/VIX(株)が同時騰勢なら“政策/信認ショック”色。
checkしておきたいウォッチリスト
- FX:DXY、USD/JPY(145/140)、EUR/USD(1.10/1.08)、CNHフィックス乖離
- 金利:米2年–10年の形状、TIPSブレークイーブン、Bund–BTP
- クレジット:CDX IG/HY、EMBIG、欧州Periphery
- ボラ:MOVE、VIX
- コモ:WTI/Brent、LME銅在庫、金(名目/実質金利との相関)
- フロー:ETF資金、MMF残高、CFTC先物ポジ
まとめ(世界版)
- 25bp:グローバルには“適温緩和”。ドル軟化・金利低下で資産価格に穏やかな追い風。
- 50bp:短期リスクオンでも、信認・タームプレミアムの揺らぎで後のボラ肥大化に注意。
- 見送り:ドル高/金利高でリスク資産に逆風。ただしFRBの独立性は最も明確に守られる。
要点:世界は“水準”より“メカニズム”で動きます。ドル・米金利・政策信認の3点を同時に見るのが、波及の大きさと持続性を測る最短ルートだと言えます。
■ 結論──FOMCは“金利”ではなく“正統性”を問われる舞台
今回のFOMCは単なる利下げ幅を決める会議ではなく、「FRBは誰のために、どの正統性に基づいて政策を行うのか」という根源的問いが突きつけられています。
- 雇用統計は前年比で91万人の雇用消失を露呈。
- インフレは高止まりし、急速な利下げは1970年代の失敗を想起。
- 市場・政権・FRBの三者が正面衝突。
👉 9月会合の本当の焦点は「米国金利利下げ幅」だけでなく、「FRBが独立性と正統性を維持できるか」どうかも非常に大きな注目ポイントになります。
この帰結次第で、米国経済だけでなくドル基軸、さらには世界金融秩序の信認までも左右される可能性が出てきます。
ファンダ的思考でいきますと、FRBが金利を下げる可能性は100%ではなく、同様に金利を現状のままホールドする可能性も0%ではありません。
ありとあらゆる可能性をシュミレーションし、どの可能性が1番高いのか?に軸足を置きつつ、サプライズがサプライズにならない様に対応する事が大切です。
今回の会合を踏まえ「ふかちん&GP君のブログ読んで予習しといて良かった」となる事を切に祈っております。
懸念事項:制度の独立性が崩れた場合
- 中央銀行としての地位の危機:独立性喪失は近代金融の根幹を崩す。
- 米国債市場の不安定化:タームプレミアム上昇で長期金利不安定。
- ドル体制の危機:ドル信認喪失でユーロ・人民元・金に侵食される可能性。
- 世界金融秩序の動揺:資本移動や為替ボラ拡大が不可避。
これは単なるFOMCの決定ではなく、制度的リスクそのもの。だからこそ9月会合は歴史に刻まれる“正念場”となる注目の会合となるのです。
出典
- BLS「Employment Situation Report (Aug 2025)」
- BLS「Benchmark Revision: QCEW data」
- U.S. Bureau of Labor Statistics CPI release (Sep 11, 2025)
- Reuters: “US weekly jobless claims increase as labor market softens”
- AP News, Bloomberg, WSJ, FT 各社報道